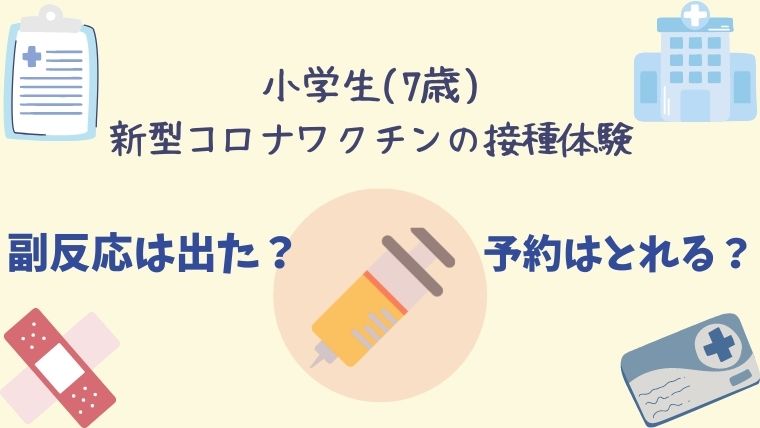小学校へ入学予定のお子さんが、入学前に行うのが就学時健康診断(就学時健診)です。
保護者の方も、5~6歳の時に経験されているのではないでしょうか?
でも、どういったことをしたのか覚えていますか。

チューリップの絵を描いた
記憶がある…
いざ、わが子が就学時健診を受けるとなると、うちの子は大丈夫かしらと不安になりますよね。
親子で事前に確認しておくと安心です。
わたしの地域では9月に通知がきて、10月頃に『就学時健診』が実施されます。
その時の様子を記事にしたので、参考にしてみてくださいね。

平日の午後に行います。在学中の児童は健診の時間にかぶらないよう、すでに下校していました!
就学時健康診断とは?

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の規定により、就学予定者の状況を把握して、保険上必要な助言を行う目的

入学後も元気に学校生活が送れるように、心身の発達確認をしましょうってことかな
この就学時健康診断は、今まで見落とされてきた疾病や障害を発見する機会でもあるので、必ず行きましょう。
一般的には、入学予定の小学校で行われることが多いです。
そのため、来年から同じ教室で学ぶ友達と、初めて出会う場にもなります。
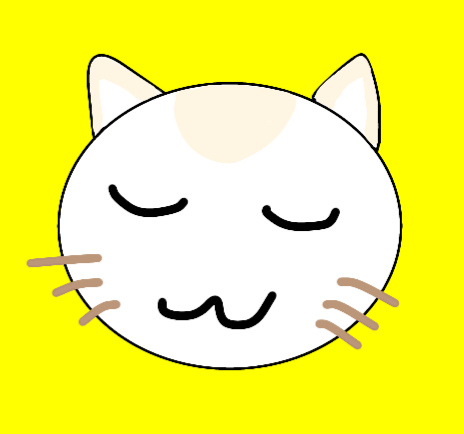
保護者同士もね!

ママ友とか…ドキドキする
(人見知り)
持ち物
9月頃に届く『就学時健康診断のお知らせ』には、健診内容と事前に記入する調査票、当日持参するものなどが記載されているお手紙が入っています。
- 健康調査票
- アレルギー調査票
- 母子手帳
- 上履き
- 水筒(水分補給のため)
子どもの服装は、自分で脱ぎ着ができるものを選びましょう。
体操服などのように上下が分かれている方が、スムーズに健診できます。

ワンピースは厳禁です!
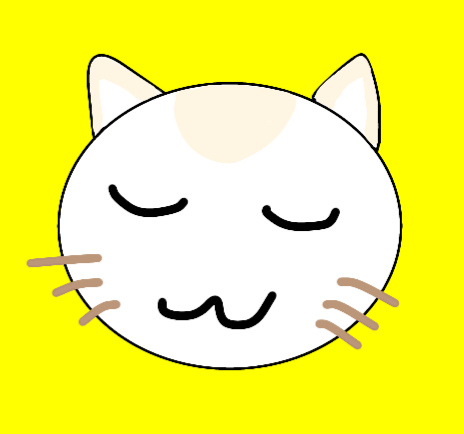
身長を測るから、頭のてっぺんおだんご結びもNGよ
子どもに付き添うので、保護者用の上履きも必要です。
移動で階段をあがる場合もあるので、スリッパはやめておきましょう。
もしこの機会に購入する予定があるなら、黒っぽい室内履きを選ぶといいでしょう。
今後行われる入学説明会や保護者会、入学してからの授業参観など、校内に入る機会が増えます。
フォーマルウェアに合った室内履きだと、どんな場面でも使えるので便利ですよ。

折り畳みができて携帯できるので重宝してます!
就学時健診ですること

保育園や幼稚園でも、内科健診と歯科検診はありましたね。
就学時健康診断は、その小学校に入学予定の子どもが集まって集団で行います。
子どもの人数も多いし、知らない先生や大人。
兄姉がいたら別ですが、初めて小学校へ行く子もいますね。
いつもと環境が違い、子どもは不安になるかもしれません。
事前に何を何のためにするのかを説明をしておけば、スムーズに健診が受けられるはずです。
- 集合
・保護者と一緒に来校
・保育園・幼稚園のバスで来校
(保護者と合流) - 受付
学区ごとに受付
グループ分けされ保護者と行動
(コロナ前は6年生が引率) - 身体的検査
グループごとに各健診場所へ
- 知能検査
保護者と別れ、子どものみ教室へ
保護者は別室待機 - 保護者合流
教室へ子どもを迎えにいく
- 帰り
身体的検査
身体的検査場所へは子どもと一緒にまわりましたが、検査を受けるときは子どもだけ。
基本的に、親は荷物持ちでした。

側で見られないから
ちゃんとできているか不安…
- 身長・体重測定
- 内科健診
- 歯科検診
- 視力検査
- 聴力検査

息子、聴力検査は初めて!
ちゃんとできたのかなぁ?
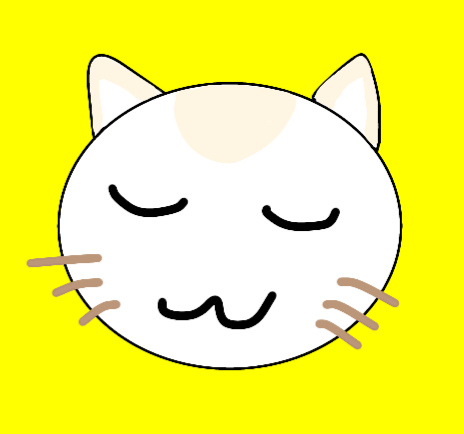
先生がちゃんと教えてくれたので
大丈夫です!
知能検査
一般的に精神発達や言語、情緒の状況を確認します。
健診を通して得られた子どもの様子や結果から、就学先を決める際の判断材料の一つとします。
| 精神発達 | 名前や性別などの意味を理解している おはじきや絵カードを使って指示された行動ができる (指示を理解しているかも確認) |
| 言語 | 音は正確に言葉になっているか 発音は正しいか |
| 情緒 | 検査中の子どもの様子を観察して判断 |
子どもは教室で検査。
保護者は別室で待機でした。
ペーパーテストはなかったようです。
先生やお友達と話したり、聞いたり、遊んだりしたーと言っていました。

息子から聞いた話なので
正確ではありませんが
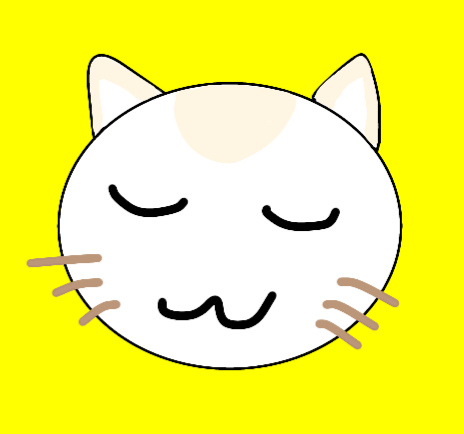
楽しかったよ?
私立小学校や地域によっては、面接やペーパーテストがあるかもしれませんね。
就学時健診まとめ

初めてのお子さんだと、何をするのも初めてで、親も子も不安ですよね。
事前に何のために何をするのか、一緒に確認できると安心です。
就学時健診は、子どもの発達を確認できるのはもちろん、小学校に少しでも慣れる良い機会になります。
小学校入学まであと少し。
2月頃には保護者への『入学説明会』が行われます。
あっ!そうそう。問題がなければ就学時健診の結果は、保護者に知らされません。
問題はなかったとはいえ、教えてくれてもいいのにね。
※この記事はプロモーションを含みます。
※2022年9月の情報です。